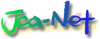- Log in to post comments
JCA-NET理事会は下記のパブリックコメントを本日送付しました。
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針(案)に関する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mo…
__________________________________________________
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防
止のための基本的な方針パブリックコメント
JCA-NET理事会
__________________________________________________
2025/11/23
Table of Contents
_________________
1. 違憲
2. 利用者個人の権利無視
.. 1. 令状主義
.. 2. 情報開示、異議申し立て
.. 3. 個人が特定可能な場合への歯止めがない
.. 4. 外国政府への情報提供と人権侵害の問題
3. 「方針」の必要性への疑問
1 違憲
======
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下本法
と記す)は、憲法が私たちの権利として明記している「通信の秘密」を根本か
ら侵害するものであり、本法に基づく「重要電子計算機に対する特定不正行為
による被害の防止のための基本的な方針」(以下「方針」と記す)の制定そのも
のに反対である。
「方針」の基本的な立場は、政府や民間企業などが通信情報をより幅広く利用
できるような制度的枠組の構築を目指すために、通信の秘密を国家の政策目標
に従属させて可能な限り狭く限定しようとするものであって、憲法が保障する
「通信の秘密」の権利を根底から侵害する。
この原則的な立場を表明した上で、以下、具体的に問題を指摘する。
2 利用者個人の権利無視
======================
「方針」は、通信の当事者、通信サービスを利用する個人でありまたコンテン
ツ――文字、画像、動画、コンピュータ・プログラム等形式を問わない――の
制作者でもある利用者個人の権利を無視している。
また通信事業者は、メタデータも含めて、意図した相手(受信者)のみが通信情
報にアクセス・利用できるように送受信に責任をもち、利用者の許可なく政府
に通信情報を提供することは憲法上許されない。従って協定を結ぶこと自体が、
通信の当事者の権利を侵害することになる。
通信情報のコンテンツ作成主体はサービスの利用者(通信の当事者)である。通
信事業者は、通信情報の送受信を媒介・管理するのみであり、所有権等を有さ
ない。政府に至っては、通信サービスの媒介・管理者でもなければ通信情報の
所有権者でもない。通信情報は通信の当事者である個人に帰属するものであり、
通信情報の保護の法的制度的枠組は、通信の秘密はもとより、思想信条の自由
や出版の自由など基本的人権の根幹に関わる。方針は、この権利の枠組を否定
するものである。
2.1 令状主義
~~~~~~~~~~~~
通信情報は通信の当事者である利用者個人に帰属するものであることから、憲
法35条が明記する「侵入、捜索及び押収を受けることのない権利」によって保
護されるものである。
「方針」は、通信情報の収集について裁判所の令状を要件としていない。監理
委員会は裁判所のような中立的な司法機関ではない。むしろ通信の当事者の権
利を弱めることに加担しかねない組織である。
当事者の許可なく外国を含む政府や政府を介した民間による通信情報の利用は
明らかな憲法違反である。本「方針」では、司法の役割への言及が一切みられ
ないことも含めて、通信の秘密に関する権利侵害を制度化するものである。
「方針」では、アクセス・無害化についても司法の介入を認めていない。これ
は、裁判所の令状に基づいてアクセス・無害化を執行した米国の事例よりもさ
らに後退している。私達はアクセス・無害化措置そのものに反対であるが、最
も侵襲性が高く、令状は必須の条件である。
2.2 情報開示、異議申し立て
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「方針」は、通信情報の提供や利活用を通信事業者、政府省庁、民間事業者の
間の問題としてのみ取り上げている。通信の当事者個人は、自分の情報であり
ながら、意図しない第三者に利用されていることすら知らされない。どのよう
な通信情報が、どのような理由・目的で通信事業者から政府等に提供されたの
かについて、知る権利がある。「方針」には知る権利への言及がない。
また、通信情報の提供・利用について、間違いや冤罪といえる場合の救済の道
がなく、通信当事者が異議申し立てを行う制度的な枠組もない。
2.3 個人が特定可能な場合への歯止めがない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「方針」では、通信情報を個人が特定されないように加工処理するかの文言が
多くみられるが、「分析の対象となる機械的情報に対して他の情報と照合しな
い限り特定の個人を識別できないようにする非識別化措置を講ずる」(p.17)と
ある。機械的情報に限らず収集情報を他の情報と照合することは禁じられてお
らず、結果として個人が識別可能であることを容認しており、歯止めがない点
は、認められない。
2.4 外国政府への情報提供と人権侵害の問題
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「方針」は「同意によらずに通信情報を利用する措置(外外通信目的送信措置
等)」で、外国における当事国の同意や了承のない情報収集活動を認めている。
これは、日本によるスパイ活動を制度化する枠組であり認められない。この規
定は、国内法、国際法、当事国の国内法にも抵触しかねず、日本政府や通信事
業者が深刻な人権侵害の加害者になりうる規定であって、容認できない。
3 「方針」の必要性への疑問
==========================
サイバー攻撃が深刻な事案となる問題を私たちは認識している。しかし、その
多くは、警察や自衛隊も含む政府の治安機関によらなくても解決可能であり、
私たちの基本的人権を大幅に制約しなければならないこととは言えず、「方針」
のような枠組は必要性がない。